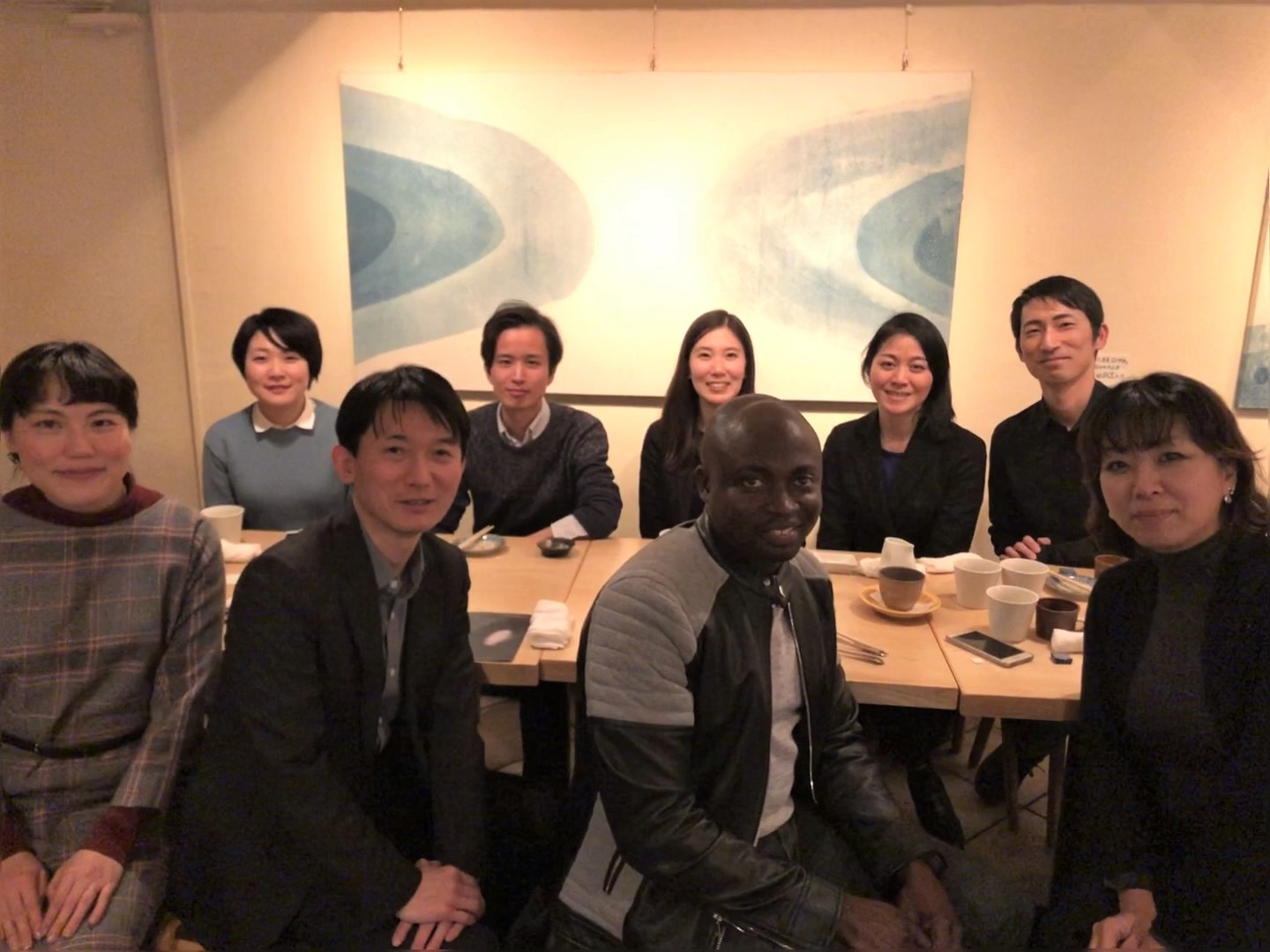越境文化演劇における感情の諸相
Facetten der Gefühle im Transkulturellen Theater
科研プロジェクト「越境文化演劇研究――異他の視点からの演劇文化論」
慶應義塾大学文学研究科プロジェクト「文化多様性の再考――人文学研究の視点から」
開催日
2020年2月9日(日)
会場
慶應義塾大学三田キャンパス 南館5階 ディスカッションルーム
| 平田栄一朗 | 挨拶と導入 |
|---|---|
| コク・G・ノノア(ルクセンブルク大学博士研究員) | 越境文化的な演劇理解における感情と情動の演出 |
| 栗田くり菜(慶應義塾志木高等学校非常勤講師) | 境界上の笑い ?― ゼルダー・ゾムンヂュによる「我が闘争」の朗読パフォーマンス |
| 谷本知沙(慶應義塾大学博士課程) | 読書行為における越境──多和田葉子の詩「Die 逃走 des 月s」を例に |
| 北川千香子(慶應義塾大学准教授) | 凍りついた感情――サルヴァトーレ・シャリーノのオペラ《氷から氷へ》への注釈 |
3年にわたる科研プロジェクト「越境文化演劇研究」の総括として、音楽劇とパフォーマンスを主な対象とした国際シンポジウムを開催しました。
音楽と感情、芸術鑑賞と感性の関係は普段の音楽鑑賞の経験から自明であるように思えますが、未知の領域や、興味深い考え方が新たに引き出されるテーマでもあります。
ベルンハルト・ヴァルデンフェルスが演劇を「異他的なものの場」と称し、またギュンター・ヘーグが「他者へ目を向けるための媒体」と表現したとおり、古今東西の演劇において「異他的なもの」、特に「固有のもの」(das Eigene)と「異他的なもの」(das Fremde)との出会いや衝突、拮抗は、物語を推し進める原動力であり続けてきました。
オペラ芸術もまた「異他的なもの」の存在を糧に発展してきたと言えるでしょう。
18世紀後半以降は、中東やアジアなどの遥かなる異国の地を舞台にしたり、物語や音楽に異国的な要素を取り入れたりしたオペラがヨーロッパで流行しました。
そうした背景から、オペラ芸術はもっぱら、自文化と他文化の自明性を前提としたインターカルチュラリティ(異文化)の観点から論じられてきました。しかし、グローバル化した現代のオペラにおいては、「固有のもの」と「異他的なもの」を対置させるような理解モデルは通用しなくなってきています。
例えば、能を題材として創作されたオペラを見たとき、現代の日本人は能を果たして「固有のもの」と捉えるでしょうか。むしろそれはすでに「異他的なもの」となってしまっているかもしれません。
そもそも、オペラにおいて「固有のもの」と「異他的なもの」とは一体何であり、それはいかに表象され、またいかなる問いを我々に投げかけてきたのでしょうか。越境文化的演劇という分析視角?―ヘーグの言葉を借りれば「思考および行為の包括的かつ文化的な実践」?―は、こうした問いに切り込む有効な手段と言えます。
オペラや演劇で「固有のもの」と「異他的なもの」が主題化されるとき、そこには常に感情が付随します。とりわけオペラでは感情がその核心をなしています。
歌唱やオーケストラの音楽は「感情の言語」として登場人物の感情表現を担うと同時に、それらは観客の感情に強く作用し、また感情を喚起する媒体でもあるからです。それゆえ、アレキサンダー・クルーゲはオペラを「感情の発電所」と表現しました。
それはオペラ、つまり観客を圧倒し、オペラの中に没入させ同化させるような、とりわけ19世紀の総合芸術としてのオペラに対して向けられた言葉です。総合、統一体、文化的アイデンティティといった幻想を解体し、むしろ断絶、亀裂、中断にフォーカスする越境文化演劇は、総合芸術としてのオペラの対極に位置します。
にもかかわらず、越境文化演劇の提唱者であるヘーグは、オペラこそが越境文化演劇の模範であると指摘しています。トランスカルチュラリティ(越境文化)と感情との関係に着目してオペラを再考することで、どのような新たな側面が照らし出されるでしょうか。
シンポジウムではオペラを中心に、文学や演劇全般をも視野に入れながら「固有のもの」「異他的なもの」と感情の関わりについて議論します。